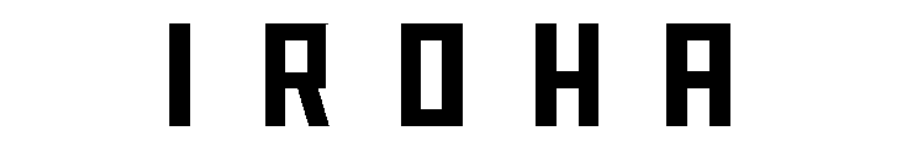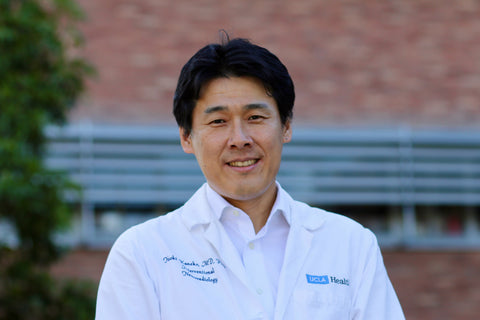
医療技術の進歩 // 金子直樹
神経血管内治療の推進
金子直樹氏は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)デイビッド・ゲフィン医学部の放射線科助教授であり、インターベンショナル・トランスレーショナル・リサーチ・ラボ(ITRL)の所長です。金子氏は東北大学で医学博士号と博士号を取得し、日本の自治医科大学で脳神経外科の研修を修了したほか、ニューヨークのアルバート・アインシュタイン医学部で研究員を務めました。金子氏は神経血管内手術を専門とし、脳動脈瘤、動静脈奇形、虚血性脳卒中などの脳血管障害の患者を低侵襲技術で治療しています。同氏の研究は、脳動脈瘤などの神経血管疾患の病態生理の解明と、新しい神経血管内デバイスの開発に重点を置いています。
いろは:これまでの仕事、プロジェクト、取り組みについて教えてください。
直樹:私は脳血管内治療の専門家として、低侵襲手術で脳の血管疾患を治療しています。例えば、血栓が脳の血管を塞ぐと、回復不可能な損傷を引き起こし、麻痺や言語障害などの生涯にわたる障害につながる可能性があります。私たちは、X線ガイド下で血管系を通してカテーテルやデバイスを誘導し、頭蓋骨を切開せずに血栓を取り除くことができます。この脳血管内治療は、従来の開腹手術よりも侵襲性が低く、鼠径部または手首を小さく切開するだけで済みます。重大な脳障害が発生する前に血栓を取り除くことで、永久的な神経学的欠損を予防し、患者が通常の生活に戻ることができます。脳血管内治療は開腹手術よりも侵襲性が低いですが、血栓を取り除く際に血管を過度に引っ張ることで出血する可能性があるなど、リスクがないわけではありません。技術の進歩に伴い、新しいデバイスや技術が開発され、これらの治療はますます複雑になっています。私の主要プロジェクトの 1 つは、3D 印刷技術を使用して正確な人間の血管モデルを作成する方法を開発することでした。以前は、血管モデルの作成に 1 週間以上かかり、1,000 ドル以上の費用がかかっていました。現在、私の方法を使用すると、患者の画像データから、わずか 24 時間で、わずかな費用でリアルなモデルを作成できます。これらのモデルは、複雑な血管疾患の解剖学に対する精緻な治療を練習したり、実際の手術の前に最も安全で効果的な手法を評価したりするのに非常に役立ちます。また、私は、脳動静脈奇形などの特定の困難な疾患を患者データからモデル化する先駆者でもあります。この進歩により、医師研修生にユニークなトレーニングの機会が提供され、塞栓物質を使用して疾患を治療するスキルが向上しました。これらのモデルは現在、UCLA だけでなく、研修生の実践的なトレーニング ツールとして世界中で使用されています。これらの技術革新を通じて、神経血管内治療の安全性と有効性が向上し、患者は脳卒中の深刻な結果を回避し、治療後にもっと普通の生活を送れるようになりました。
いろは:どんなプロジェクトを 現在取り組んでいることは何ですか?
直樹:臨床的には、最新の神経血管内治療を用いた脳卒中患者の管理に重点を置いています。教育面では、国内外で積極的に教育と指導に携わり、世界中の医師に最新の神経血管内治療技術を指導するための会議や実地コースでセッションを主導しています。私の研究は、特に神経血管疾患における血流力学と反応に重点を置いています。関心のある分野の 1 つは脳動脈瘤内の複雑な血流で、これは現在ではコンピューター シミュレーションで計算できます。多くの研究で、動脈瘤内の異常な血流パターンと成長または破裂の間に相関関係があることが示唆されています。しかし、これらのパラメータを予測目的で実際に適用することは、これらの血流が血管壁に実際に及ぼす影響を理解することが困難なため、まだ十分には進んでいません。この問題を解決するために、私は 3D 印刷技術を使用して、血管内皮細胞で覆われた解剖学的に正確な動脈瘤モデルを作成しました。これにより、これらの細胞が異常な血流にどのように反応するかを視覚化し、評価することができます。このアプローチにより、私たちの理解が深まり、動脈瘤破裂のより優れた予測モデルにつながる可能性があります。この研究は、NIH、脳動脈瘤財団、寛大な寄付者からの助成金によってサポートされています。さらに、私は神経血管内手術の専門知識を活用して、新興企業や大手医療機器会社向けに新しい神経血管内デバイスの開発と評価に関するコンサルティングを行っています。私が開発した血管モデルは、新しいデバイスが実際の人間の血管状態で安全かつ効果的に機能することを保証するのに役立っています。私は、これらのイノベーションが血管疾患に苦しむ患者に本当に役立つかどうかについて、臨床医の視点を提供しています。これらの新しいデバイスが規制当局の承認を得て、臨床現場で人命を救うために使用されるのを見るのはやりがいがあります。
いろは:今後の予定を教えてください。
直樹:将来は、自分の医療機器を開発したいと思っています。日本と米国での臨床経験を基に、現在は医療分野の特定の課題に対処する革新的な機器の開発に取り組んでいます。神経血管内治療やその他の医療機器用の新しいツールの設計と試作を行っています。現在、動物実験を実施していますが、これはこれらの機器を患者に届けるための重要なステップです。医療機器の開発と承認は複雑で、多くの規制上のハードルがありますが、私はそのプロセスのあらゆるステップが興味深く、刺激的だと感じています。自分の発明に加えて、他の有望なアイデアの開発を支援することにも尽力しています。限られた時間の中で、大きな影響を与え、できるだけ多くの命を救う可能性のあるイノベーションに焦点を当てています。最終的には、患者ケアの改善にできる限り貢献することが私の目標です。自分が開発した機器を通じてであれ、他のイノベーターへのサポートを通じてであれ、世界中の患者の生活に意味のある変化をもたらすために一生懸命働いています。それは、医療技術の進歩だけにとどまりません。それは、困っている人々のために本当の変化をもたらすことです。
いろは: アジア人に対する憎悪についてどう思いますか? この問題の解決にどのような貢献をしてきましたか?
ナオキ:私は、偏見を排除することが極めて重要な資金調達や採用審査などのプロセスに関わってきました。憎悪という現象は複雑で厄介な問題です。憎悪などの感情はさまざまな原因から生じますが、多くの場合、個人的な経験やメディアの報道に影響された無意識の偏見に根ざしています。理解すべき重要な点は、無意識の偏見が、私たちが気付かないうちに私たちの認識や反応を大きく左右する可能性があるということです。特定のグループの誰かに出会ったとき、これらの偏見は否定的な感情や憎悪さえ引き起こす可能性があります。これは、認識された脅威から身を守るという人間の基本的な本能から生じている可能性があり、歴史的にそれが味方と敵を区別するのに役立ってきました。残念ながら、これらの否定的な感情は、罪のない人々に対する有害な行動につながる可能性があります。そのような行動は決して正当化されるべきではありません。このような問題に対処するには、これらの偏見を認識し、積極的に取り組むことが非常に重要です。他者を理解し、理解してもらうための相互の継続的な努力は、どの社会でも重要ですが、特に複雑な偏見や差別の問題に対処する場合は重要です。 UCLA では、学術的および職業的環境における多様性と公平性を確保するために多大な努力が払われています。教員は、多様性と公平性に関する定期的な研修を受けています。これらの努力は、無意識の偏見を認識するのに役立ちます。この IROHA ジャーナルのようなものも、私たちが何をしているのか、そしてアジア人に対する憎悪にどのように対処しているのかを認識する上で非常に重要です。私たちは、認識の起源を理解し、誤解を正すことに積極的に取り組み、憎悪を防ぐ必要があります。
いろは:あなたの経歴を踏まえて、あなたの後を継ごうとする若者に何かアドバイスやメッセージはありますか?
ナオキ:自分の分野の広さと深さを理解することが重要です。多様な貢献の上に成り立っており、先駆者から学ぶことは不可欠です。自分の分野の歴史的背景と先駆者を理解することは、非常に貴重です。多くの場合、大きな進歩は共同の努力によってもたらされます。いつ協力すべきかを知ることは、効率的であるだけでなく、経験を豊かにし、楽しいものにもなります。自分のキャリアを長期的な旅として考えてください。忍耐、粘り強さ、適応して学ぶ意欲が必要です。個人的な成功だけでなく、自分の分野内外のチームメンバーや協力者に良い影響を与えることも目指してください。このバランスの取れたアプローチにより、キャリアがやりがいのある影響力のあるものになると信じています。
いろは:仕事以外で、今一番興味があることは何ですか?
ナオキ:私は仕事でよく海外を旅行しますが、訪れた都市にどっぷり浸かる機会があれば、そのすべてを楽しんでいます。歴史的な場所を訪れるだけでなく、地元の市場や人気のエリアを探索して、地元のライフスタイルを理解するのも好きです。地元の食べ物を食べるのが大好きなので、地元の料理を味わったり、地元のワインを飲んだりするのは、私にとって大きな喜びです。可能な限り、地元の友人に案内してもらうのが好きです。観光しながら歴史や文化について学ぶのはとても楽しいです。
執筆:ジェシカ・ウールジー/ 写真:
ウェブサイトリンク|ソーシャルリンク | ソーシャルリンク